「生き物が好き」でバイオ系に進んだあなた。
 学部生
学部生せっかく大学で生物を学んだから、
その知識を活かして研究職で活躍するぞ!
そう考えていませんか?
実はその道、想像以上に狭き門です。
生物学部を卒業しても、希望通りの職に就けない人が多く、就職に苦労するケースも少なくありません。
本記事では、実際にバイオ系の大学院を修了した筆者が、就職が厳しいと言われる理由と、これからの対策について解説していきます。



本記事ではこれらの疑問を解決できます。
- バイオ系の就職先が悲惨な理由
- バイオ系の闇とは何か?
- バイオ系の学生は今後どうすべきか



私も就活時には、希望の仕事に就けなくてめちゃくちゃ苦労しました!就活で地獄を見たエピソードを知りたい方はこちらの記事も読んでみてください。
なぜ生物学部の就職先が悲惨なのか?


ネットで調べると、「バイオ 就職 悲惨」というワードが出てきます。
なぜ、生物学部の就職先が悲惨だと言われているのでしょうか?
その理由は、以下の3点となります。
- バイオ系の専攻を活かせる就職先がないから
- バイオ系の求人に派遣が多いから
- 博士課程の末路が地獄だから
それでは順次解説していきます。
バイオ系の専攻を活かせる就職先がないから
バイオ分野の就職先は本当にありません!
バイオ学生の皆様は細胞やタンパク質の機能を研究している方が多いですが、それらを活かせる企業は非常に少ないです。



専攻を活かせる職種は細胞技術者か研究職ぐらいですかね。


確かにindeedのような求人サイトを隈なく探せば、バイオ分野の企業はたくさんあります。
しかし、ほとんどの企業が実務経験3年以上の即戦力を求めていたり、契約社員やアルバイト登用がザラだったりと新卒で尚且つ正社員のバイオ系の企業はほぼないです。
私も生物系の大学院で研究していた時がありましたが、同期や先輩がバイオ系の企業に就職した知らせはほとんど聞きませんでした。
ITコンサルタントだったり、塾講師だったりと専攻と関係ない仕事が多かったですね。
まあ、大抵の学生は食品業界や化学業界の企業に就職するのですが。



特に驚いたのが、学部の時の就職説明会で生物分野に全く関係のない靴屋に就職したOBを紹介していたことです。
就職説明会ですら、研究分野をそのままいかせる企業に就職した学生はほとんどいませんでした。
東大や旧帝大などを卒業している超エリートだったら、まだ就職先があるかもしれませんが、MARCHレベルの平凡な学生だと実際こんなもんです。



でも、実際にバイオ系企業の研究職についている学生もいるよ!



残念ながら、バイオ系企業の研究職に就けるのは一部のエリートだけです。
このように研究で学んだことを直接活かせるバイオ系の企業は採用数は少なく、限られた人しか就職できないので、専門外の就職を検討する必要があります。
大学の体験入学で大学職員から「生物学部は就職に困らない」という言葉を聞くことがありますが、あれはセールストークです。
真に受けると就職先で困ってしまいますので、これから生物分野の学部に受験する方はよく考えてから受験しましょう。



実際に私も「生物学部は就職に困らない」というセールストークを真に受けて失敗しています。
ただし、生物学部といっても、学部生ならそこまで専門性を問われないので、就職活動までに自己分析や企業分析を行い、自分の適性や社風とマッチした企業に就職するようにしましょう!
バイオ系の求人に派遣が多いから
前述しましたが、indeedのような求人サイトでは、派遣やアルバイトの求人が多いです。
つまり、正社員として採用している企業が少ないということです。
多くの派遣やアルバイトは働く期間が決められていて、契約した期間内でしか働けません。
それに派遣やアルバイトは正社員より社会的信用が低く、長い間派遣やアルバイトで働き続けていると再就職が厳しくなってしまいます。
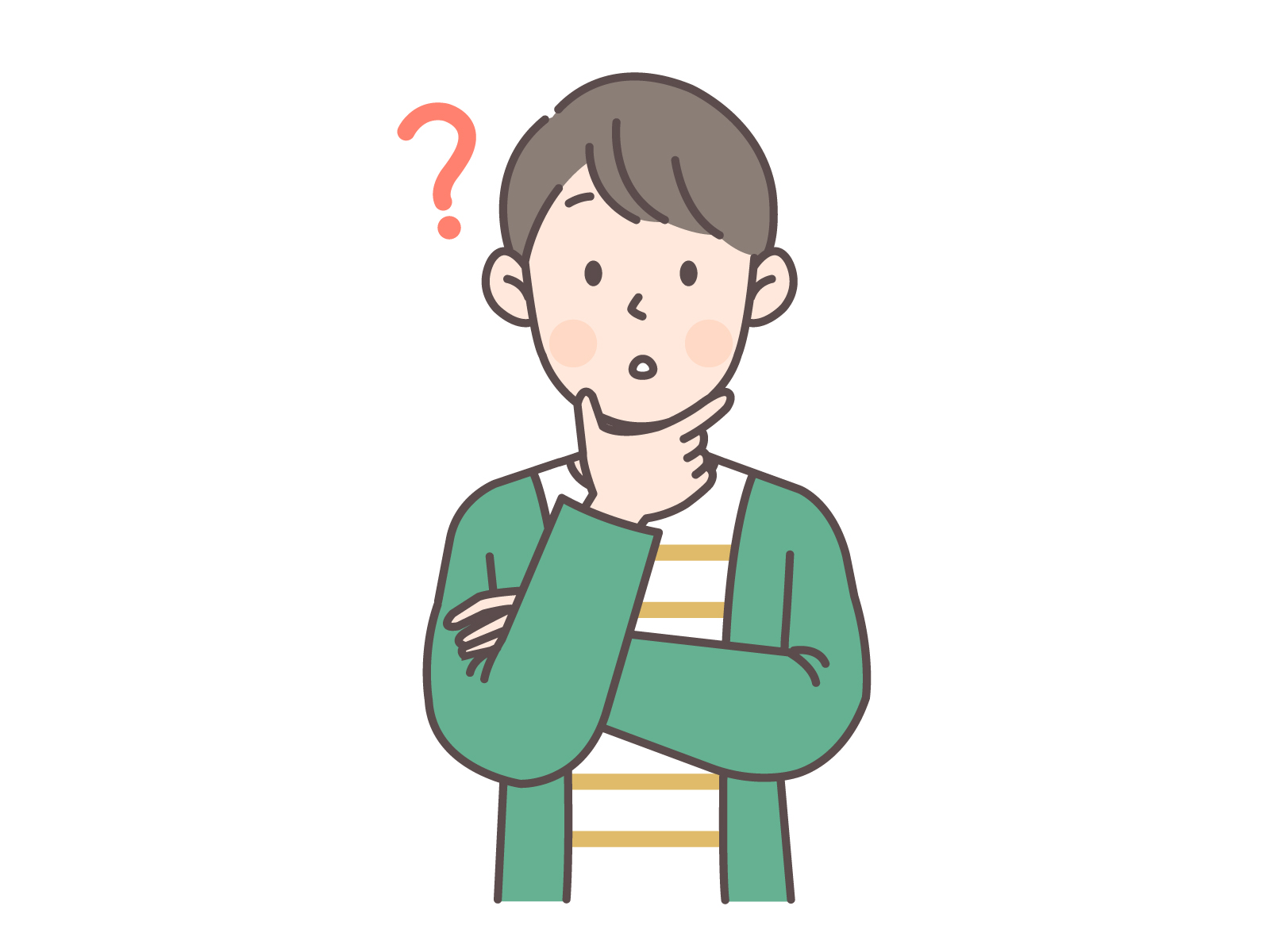
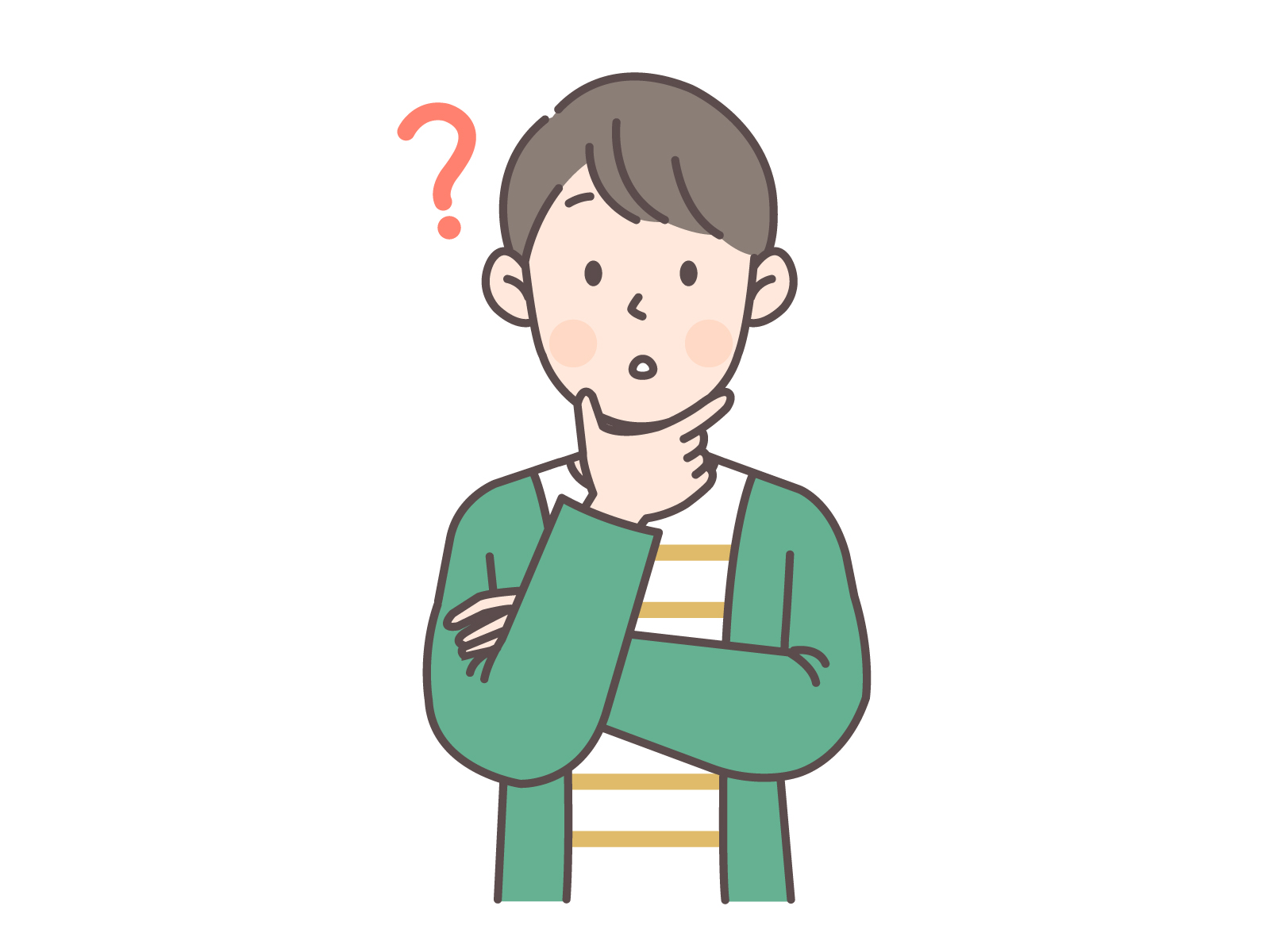
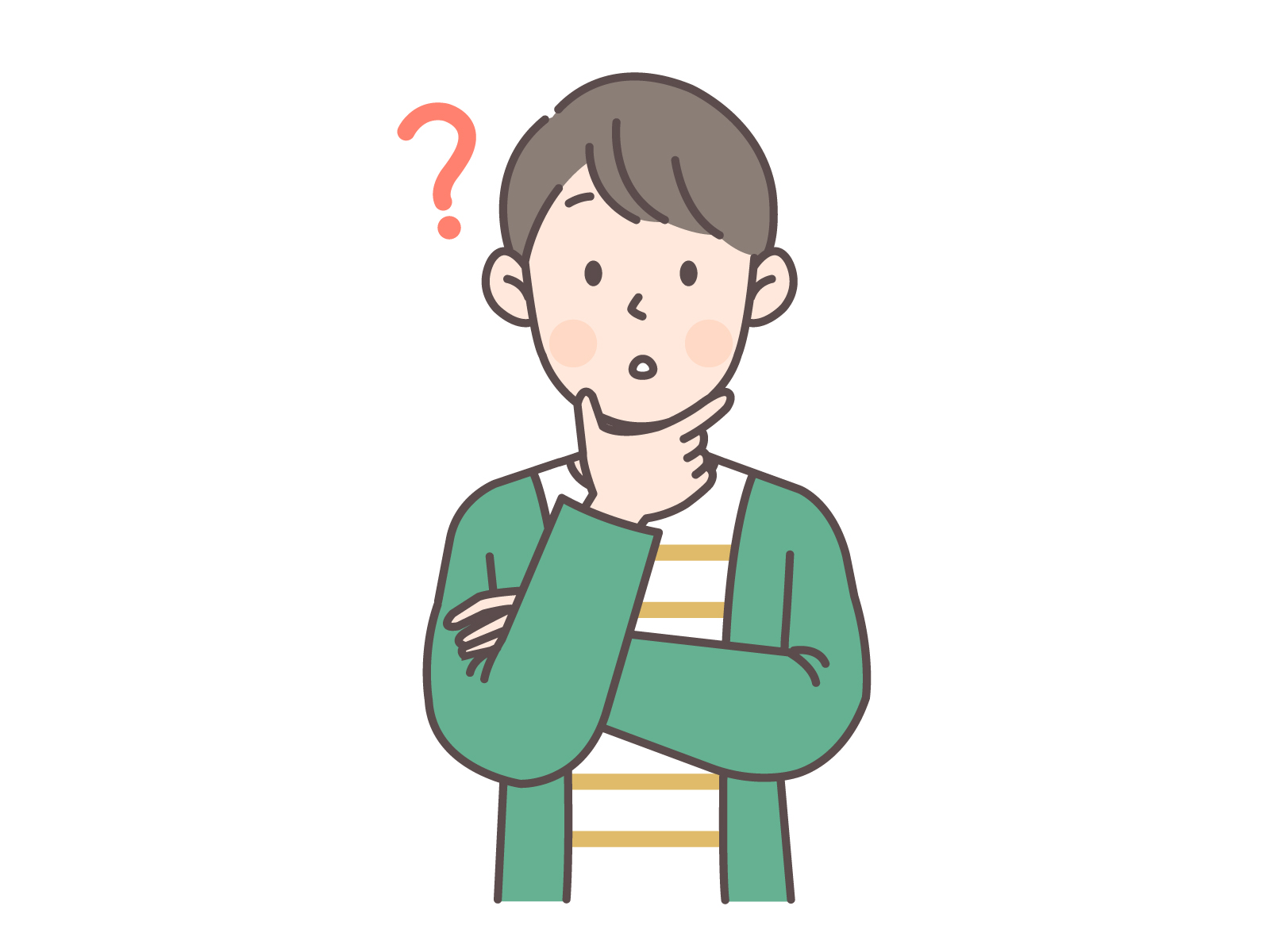
でも長く働き続けていたら、正社員として雇ってくれるって話を聞いたよ!



残念ながら、そういうケースはほぼないんだ。
また、バイオ系学生の主な就職先として大学教授やポスドクがありますが、前者は一握りのエリートしかなれず、後者は短期雇用がほとんどで安定しません。
さらに、○-ソルや○ドバンテックなどの正社員型派遣会社もあるのですが、あらゆる実験器具を使いこなせないと基本的に採用されません。
仮にそのような正社員型派遣会社に採用されたとしても、契約終了となれば、問答無用で辞めさせられ、研究職ではない畑違いの職種を紹介されることがあります。
なので、正社員型派遣会社で働いても、全く働き方が安定しません。
このことから、バイオ系の企業は非正規雇用が多く、経済的に不安定な生活を送る可能性が高いのです。
博士課程の末路が地獄だから
企業の研究職を目指すなら、博士課程には進まず、修士課程で卒業するのが最善とされています。
その理由は、博士課程に進むことで進路の選択肢が大幅に限られるからです。
博士課程修了後の厳しい現実
博士課程修了者の先輩がマイナビを利用した際、紹介された企業はほとんどなかったという話もあります。
さらに、博士課程を修了してもアカデミアのポストに就けるとは限らず、就職活動では年齢的なハンデを背負うことになります。
特に未経験分野への挑戦は困難で、新卒採用が基本である企業では、博士課程修了後の再スタートは難しいのが現実です。
博士課程進学の背景
もちろん、子供が研究への強い情熱を持ち、博士課程への進学を希望するケースもあります。
しかし、現実には教授のパワハラなどで、望まないまま博士課程へ進むケースも少なくありません。
博士課程のリスクと負担
博士課程は通常3年間ですが、優秀な学生であれば2年以内で修了することも可能です。
ただし、論文提出が遅れると卒業が遅れることも多く、特にバイオ分野では留年率が高い傾向があります。
留年すればその分学費負担も増え、経済的な負担はさらに大きくなります。
学振特別研究員になれるのは一握り
修士課程までに実績を積めば、学振特別研究員に選ばれ、2〜3年間の生活費支援を受けながら研究に打ち込むことも可能です。
しかし、この制度の合格率は10〜30%程度と非常に狭き門であり、多くの学生にとっては現実的ではありません。
博士課程修了後の就職状況
実際、博士課程修了者の約70%は定職に就けていますが、そのうち約20%は非正規雇用という厳しい現実があります。
さらに、文部科学省のデータによると、約10%は「その他」と分類されており、進学以外にも行方不明や消息不明のケースが含まれています。
特に、文系の博士課程修了者はさらに厳しい状況に直面することが多いです。
博士課程進学は慎重に判断すべき
このように、博士課程に進んだ結果、思い描いたキャリアを築けず、就職の選択肢が狭まるケースは少なくありません。
仮に博士課程を修了しても、アカデミアでのポストに就けなければ、年齢的に未経験分野への転職はほぼ不可能です。
そのため、明確なキャリアビジョンがない限り、博士課程への進学はおすすめできません。
もし新卒で博士課程進学を検討しているなら、大学院に進む前に将来のキャリアについてよく考えることが重要です。
現実を知り、リスクとメリットを天秤にかけたうえで、慎重な選択をしましょう。
【実体験】大学院に進学しても、研究職になれなかった。
私は、研究職に就くためにバイオ系の大学院に進学しました。
理由は、私の将来の夢が生物学者になることと、研究で食っていきたいと思っていたからです。
私は、これら2つの夢を叶えるために、地獄の研究生活を過ごしてきました。
夜中までかかる長時間の実験、成果主義、教授の絶え間ない𠮟責…
強いストレスに耐えつつ、落ちこぼれながらも必死で研究をし、就職活動も並行して行っていきました。
専門分野を活かした職に就くために、就職イベントに参加したり、就職エージェントに登録したりするなど、就職活動でもかなりの努力をしました。
その結果、懸命な努力も虚しく、研究職に就くことはできませんでした。
研究職に就けるのは、大学院生の中でも学会発表で優秀な成績を修め、コミュニケーション能力が非常に高い選りすぐりのエリートのみだったのです。
結局、大学院に進学して、得られたものは、「自分は研究に向いていない」という残酷な事実でした。
博士が100人いる村を知っていますか?
悲惨な末路を迎える生物学部の学生があまりにも多いので、「博士が100人いる村」という創作童話が作られてしまいます。
「博士が100人いる村」とは、博士号取得者の進路状況を「100人の博士が暮らす村」という形式でユーモラスに表現した創作童話のことです。
令和2年度のデータによれば、100人の博士のうち、18人が医師、13人が大学教員、10人がポスドク(博士研究員)、16人が企業勤務、2人が公務員、18人が他分野に転身、17人が無職、6人が行方不明または死亡しているとされています。
このように、この物語は、博士号取得者が直面する厳しい現実を風刺的に描いているのです。
動画化されているので、これから生物学部を受験する方は是非見てください。
バイオ系の学生が就職活動で成功する方法


ここまで読んで、バイオ系の就職先が悲惨であることが理解できたと思います。
バイオ系の就職先がほとんどないことを知って、絶望している学生も多いでしょう。



とはいえ、学部4年生はそこまで専門性を必要としないため、院生と比べて就職先が広いです。



学部4年なら挽回できるね!
生物学部の学生が今後のキャリアを考える際に、以下の行動が重要です。
- 研究職にこだわらない
- 研究職は競争が激しく、内定が得られないリスクが高いため、他の職種も視野に入れることが重要。
- 自己分析をする
- 適職診断ツールや就活セミナーを活用して、自分の強みや適性を把握する。
- 市場価値を高める
- IT、簿記・会計、マーケティング、ライティングなどのスキルを習得し、インターンを活用して実績を作る。
- 就職サイトに登録する
- 一般的な就活サイトだけでなく、スカウト型やバイオ系に特化したサイト(例:OfferBox、アカリク)にも登録する。
- エントリーシート(ES)の作成
- 過去のESを参考にしながら、書類選考を通過しやすい内容を作成する。
- 適性検査の対策
- 面接対策をする
- しっかりと準備を行い、論理的に話せるように訓練する。
- 内定を得やすい業界を狙う
- 不動産、金融、人材、IT、Web、代理販売、アパレル、飲食などの業界は内定を得やすい傾向がある。
- 特にIT・Web業界はバイオインフォマティクスの知識を活かせる可能性があるためおすすめ。
また、ブラック企業への就職を避けるために、口コミサイトやOB訪問を活用して企業の実態を調べることも大切です。



以下の記事では、バイオ系の学生が就職活動で成功するための秘訣をより詳しく解説しています。就活をスムーズに進めたいなら、今すぐチェックしてください。


研究職以外も狙える!市場価値を高めるおすすめスキル
バイオ系の学生が就職活動で成功を収めるためには、大学で培った専門知識に加えて、実用的なスキルを習得し、自身の市場価値を向上させることが欠かせません。
実用的なスキルは以下の通りです。
- ITスキル
- 簿記・会計スキル
- マーケティングスキル
- ライティングスキル
これから順を追って見ていきましょう!
ITスキル
近年、社会全体でIT化が急速に進んでおり、文理を問わずITスキルを持つ人材の需要が高まっています。バイオ系出身でも、ITスキルを身につけることで就職先の選択肢が大きく広がります。
ただし、プログラミングには向き不向きがあるため、最初からIT企業への就職を目指すのではなく、まずは基礎から学ぶことをおすすめします。
たとえば、Progateなどの無料サービスを使って、HTMLやPythonなどの入門講座を体験してみましょう。
自分に合っていると感じたら、プログラミングスクールへの通学を検討するのも良い手段です。



プログラミングスクールを選ぶ際は、以下の3点をチェックしましょう!
- 実務に直結するカリキュラムが組まれているか
- 経験豊富なメンターからサポートが受けられるか
- 卒業後の就職支援やコミュニティが充実しているか
独学で学ぶことも可能ですが、エラー対応や進捗の管理に時間がかかることもあるため、スクールで効率よく学ぶ方が安心です。
小学校でもプログラミング教育が始まる現代、ITスキルはあって当然の時代に入っています。バイオとITを掛け合わせたキャリアも広がっている今、早めに基礎を習得しておくと強い武器になります。
入する時代なので、流れに乗ってITスキルを身に着けちゃいましょう!
簿記・会計スキル
簿記・会計スキルは経理をする上で欠かせないスキルです。事務職や経理・会計などの職種では、学んだことが仕事に直結するので、非常に有用性のあるスキルだと言えます。
特に簿記2級を持っている方が、実際の転職で役に立ったという声も挙がっています。
事務職や経理・会計などの職種は現在も需要があるので、スキルのない人が身に着けるべきスキルだと言えるでしょう。



ただし、簿記2級を持っているからと言って必ずしも就職しやすくなるとは限らないので注意!
事務職や経理・会計などの職種に興味がない人も、簿記の知識が副業や起業に活かせたり、就活の企業研究で会社の業績を把握するのに役に立ったりします。就職の他にも様々な場面で役立つスキルなので、是非簿記・会計スキルを身につけてみてはいかがでしょうか?



簿記スキルを学ぶメリットについては、こちらの記事でも詳しく書いています!
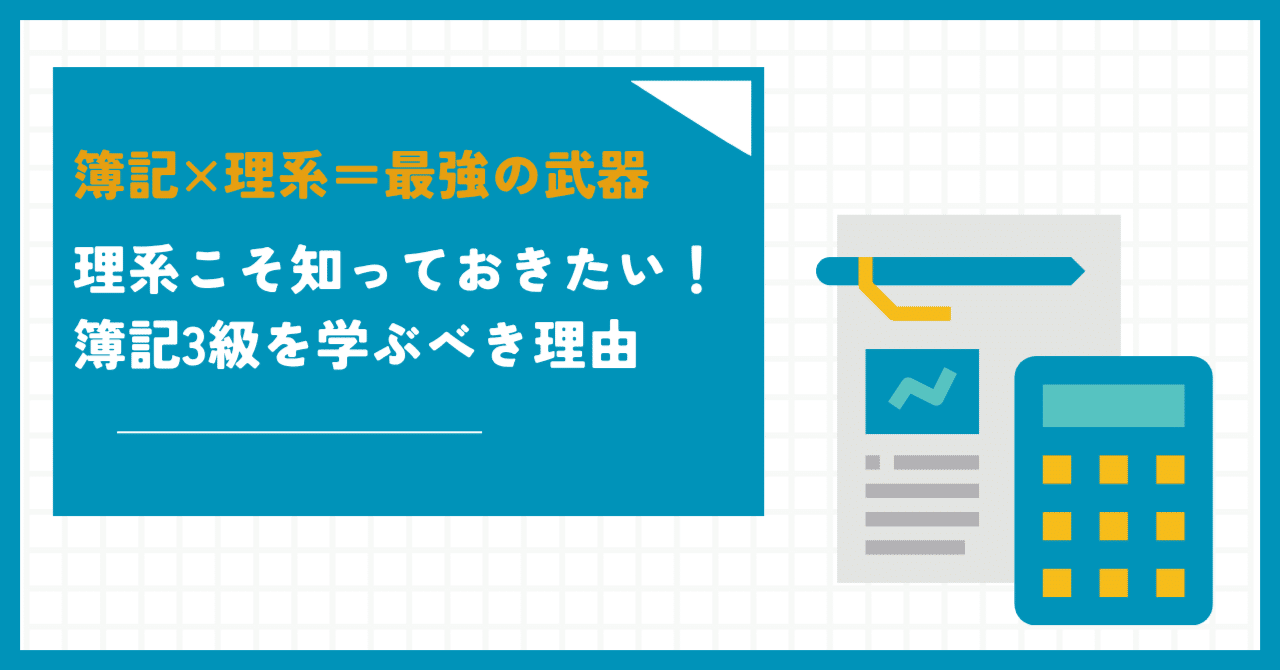
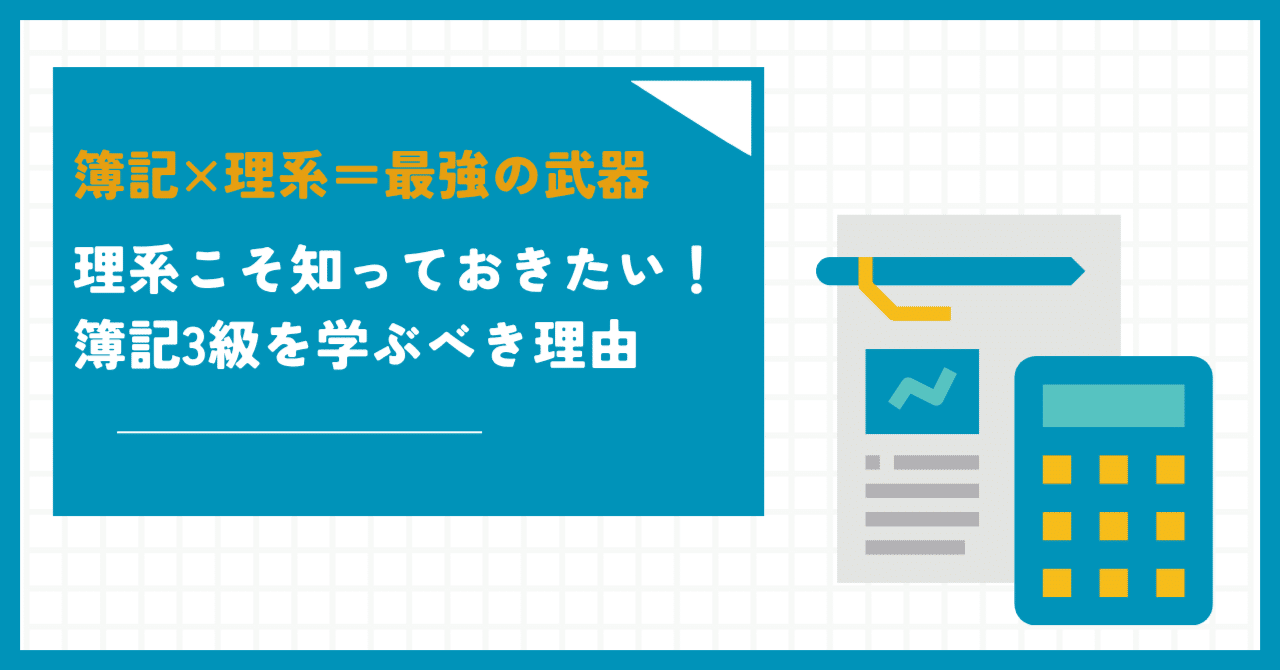
マーケティングスキル
「商品を売る」スキルは、営業や企画、Webマーケターといった幅広い職種で求められます。実は、就職活動も自分自身を企業に売り込むプロセスなので、マーケティング思考は非常に役立ちます。



マーケティングスキルを身に着けると、副業だけでなく、WEBマーケティング系の企業の就職も狙えるよ!



就職の幅が増えるのはいいね!
最初の一歩としては、X(旧Twitter)やブログなどで情報発信を始めるのがオススメです。読者目線を意識した発信は、自然とマーケティング感覚を養う訓練になります。
将来的に副業や独立を考えている人にも、マーケティングスキルは必須ですよ。
ライティングスキル
文章を書く仕事に挑戦したい人にとって、基礎をどれだけ早く固められるか は大きく成果に影響します。
文章でわかりやすく伝える力は、すべての職種で重宝されます。エントリーシートや面接時の自己PRにも、ライティング力は大きく影響します。
普段から文章に抵抗がないなら、ブログやクラウドソーシングを通じてWebライターを目指してみるのもおすすめです。
ただし、書き方の基礎が曖昧なままだと、どうしても記事の質が安定せず、伸び悩んでしまいます。
そこで初心者に強く推したいのが、『新しい文章力の教室』という一冊です。
この本は、
- 読みやすい文章の型
- 構成の作り方
- 情報の整理方法
- 読者に伝わる言い回し
- 企画書や記事構成の作り方
など、文章に必要な基礎がとてもわかりやすくまとめられています。



ヒトデさんやこまめさんなどの多くの有名なブロガーが「新しい文章力の教室」をイチオシしています!
ブログ本としてのイメージが強いですが、企画書の書き方も書いてあるので、社会人生活にも役立つ一冊です。
ライティングを勉強するなら、まずはこの一冊を読んでおくと 文章作成の迷いが一気になくなります。
まとめ
今回紹介した4つのスキルは、バイオ系出身という枠を超えて、あなたの可能性を大きく広げてくれます。
就活や将来のキャリアに備えて、少しずつでも準備を始めてみましょう。



こちらの記事では、新社会人におすすめの本を紹介していますが、
学生のうちに読んでおけば、就職後に一歩リードできるはずです。
将来に備えて、今から行動しておきましょう!


「バイオ系で就職できない…」と感じたら読むべきこと
バイオ系の就職先が見つからず、不安を感じている方へ。
そんな時は、キャリアコーチングの活用も選択肢の一つです。
プロのコーチと対話することで、自分では気づけなかった強みや適職を見つけられることがあります。
特にバイオ系のように選択肢が限られる分野では、第三者の視点が突破口になることも。
一人で悩まず、まずは専門家に相談してみましょう。新たな進路が見えてくるかもしれません。
特にバイオノミライというキャリアコーチングは、バイオ系に特化したキャリアコーチングなので、あなたにマッチしたキャリアコーチングを受けられます!この機会にぜひ利用してみませんか?


在学中なら副業を始めるのもアリ
博士課程に進学すると、研究に追われる日々が続き、経済的な余裕もなくなるケースが少なくありません。
しかし、在学中の時間を有効活用して副業を始めることで、将来的なリスクを減らすことができます。
大学生・大学院生が副業するメリット
大学生・大学院生が副業することで以下の恩恵を得られます。
- 給与以外の収入を得られる
- スキルを習得し、就職の選択肢を増やせる
- タイムマネジメント能力が向上する
業で収入を得られるようになるまでには時間がかかりますが、一度軌道に乗れば、アルバイト以外の安定した収入源を確保できるようになります。
また、副業を通じてビジネススキルやITスキルを習得すれば、研究職だけでなく、民間企業への転職やフリーランスへの道など、キャリアの選択肢が広がります。
特に、副業で培ったスキルを活かせば、研究職以外にもフリーランスや起業といった道も視野に入るでしょう。
将来的に自分のペースで働きたいと考えているなら、今のうちに副業でスキルを磨いておくことは大きなアドバンテージになります。



個人的に初期投資が少なく、様々な副業の足掛かりとなるブログがおすすめです!
隙間時間を使ってブログを書いていくと、文章が上手くなるだけでなく、情報発信力やロジカルに考える力も鍛えられます。
これらは 就活でも副業でも評価されるスキル なので、今からブログを始めておく価値はとても高いです。
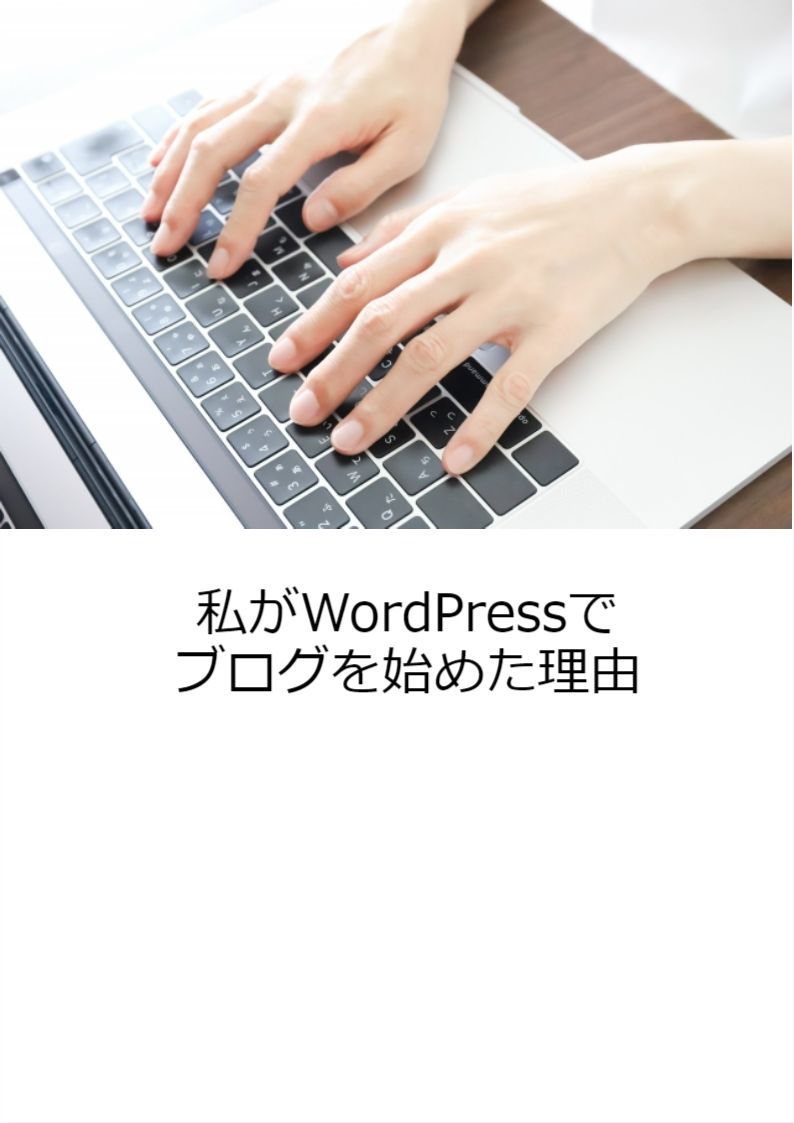
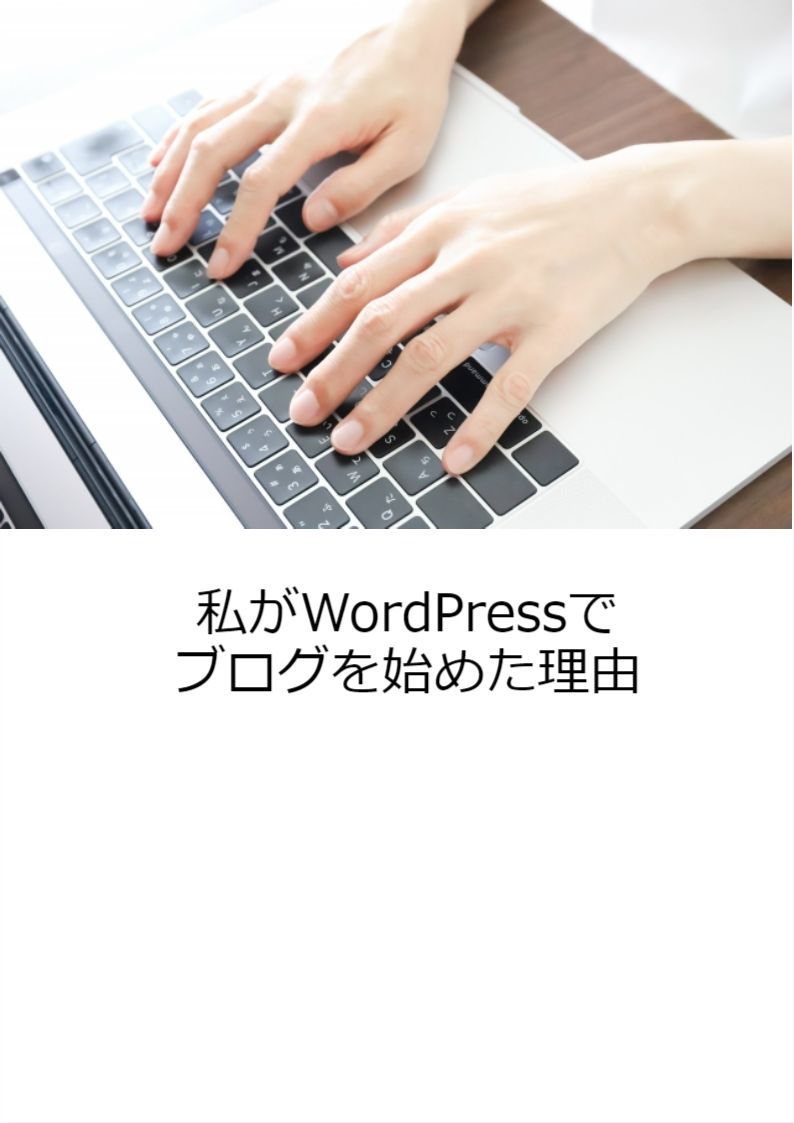
終身雇用が崩れ、会社に頼るだけの働き方が難しくなってきています。
そのため、時間に余裕のある大学生のうちに副業へ挑戦しておくと、将来の選択肢が大きく広がりますよ。
まとめ
今回の記事は、バイオ系の就職先が悲惨である理由を2つ紹介しました。
バイオ系の就職先が悲惨である理由をまとめると以下の通りです。
- バイオ系の専攻を活かせる就職先がないから
- バイオ系の求人に派遣が多いから
生物系の企業が少ないので、競争率が非常に高くなります。そのため、生物学部は職種の幅を広げる必要があります。研究職に囚われず、自分に合った仕事を探すことが大事です。
また、転職活動をイージーにするためにも自分の市場価値を高めておきましょう。生物学部の就職は本当に厳しいので、必ず就活をガチでやるようにしてください!

コメント